子供の成長に合わせて行うイベントにはお七夜、お食い初め、お宮参り、初節句などがありますが、中でも七五三は一大イベントではないでしょうか?
今回は七五三について、男の子と女の子の違いや、数え年でやるのか、満年齢でやるのかそれぞれいつ(何歳の時に)やればいいのか?を調べてみました。

七五三の時期日
七五三は、毎年11月15日に決められています。2016年の今年は15日火曜日になります。
七五三とは、今の歳まで無事に過ごすことができた感謝と、今後の成長をお祈りする行事です。では、なぜ「7」と「5」と「3」と言う数字なのでしょう?
| 年齢 | 儀式名 |
| 三歳 | 髪置きの儀 |
| 五歳 | 袴着の儀 |
| 七歳 | 帯解きの儀 |
髪置きの儀
平安時代は、「おぎゃー」と産まれてから髪を伸ばすのが許される三歳までは、男の子も、女の子も共に髪を剃りあげていました。そして、三歳になってようやく伸ばせるようになります。三歳にもなると、「もう赤ん坊ではないですよ」との意味からそうしたといわれます。
袴着の儀
五歳になった男の子だけ、その年の11月15日に袴を履いて碁盤の上に立たされました。なぜ碁盤の上なのでしょう?、
その昔、碁盤は「勝負の場」の象徴とされていました。その勝負の場に立って四方の神に拝むことにより、今後の人生において何事にも負けず勝負強い人になるとの願いが込められています。
帯解きの儀
字のごとく、帯を解く儀式です。女の子は7歳になるまで胴の部分にある紐を結んで着物を着ていました。7歳になってこの紐を外して、大人と同じ帯を付ける事が許されたといいます。
男の子の袴着の儀と同じ意味を持ちます。男5歳、女7歳にて大人と認められたのですね。
七・五・三と言う数字には、このような意味があるのです。
スポンサードリンク
男の子と女の子、七五三はいつやる!?
七五三は、3歳、5歳、7歳と一年おきにありますが、男の子も女の子も三回ともやらなければならないのでしょうか?という疑問がでてきます。
男の子は五歳だけ、女の子は三歳と七歳・・・と現代ではこのようにやることが多いと思います。しかし、本来は男の子も三歳の「髪置きの儀」はやるべきなんですね。
それは、「髪置きの儀」に男女の区分はないからです。
今でも地域によっては、男の子も三歳と五歳にやるところもあります。しかし、どうしてもそうしなければならないと言うものではなく、時代の移り変わりや、経済状況を考えて行えばいいと思います。(私見です)
七五三をやる子供の年齢は、数え年?それとも満年齢?どっち
以前は数え歳で行われていましたが、現在では満年齢で行われることが多くなっています。
満年齢とは、実年齢をいいます。すなわち生まれた年を0歳として、誕生日が来たら1歳と数えるのが満年齢。
一方、数え歳は、生まれた時点で1歳とし、年が開けて1月1日で2歳になるという数え方です。
12月31日に産まれた赤ちゃんは、産まれた日の31日が1歳で、次の日、1月1日で2歳になります。
いきなり2歳です。(笑)こういったこともありえます。
具体的に、2016年に七五三を迎えるお子さんは下記の通りです。
7歳 平成21年生まれ
5歳 平成23年生まれ
3歳 平成25年生まれ
七五三について書いてみましたが、少しはお分かりいただけましたでしょうか?
今まで、行事だからと何気に七五三をお迎えしてましたが、意味がわかれば、いつもとは違うイベントになることでしょう。
今後、お子さんが健康で、明るく素直に育ってくれるといいですね♪





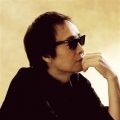





コメント